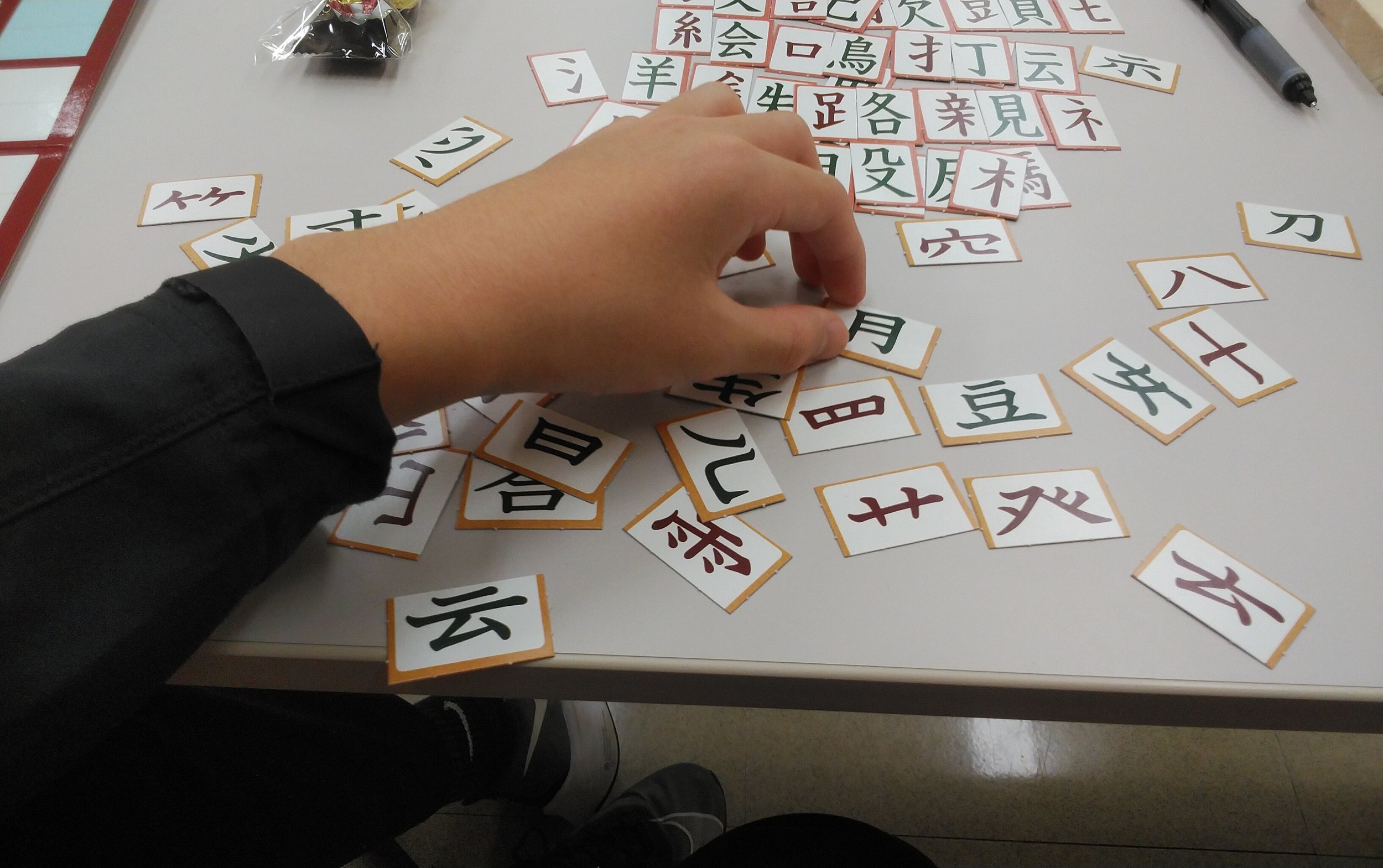■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
420時間日本語教師養成講座と日本語教育能力検定試験にチャレンジ
2024年11月10日
山上真也
海外にルーツを持つ生徒さんと日本語の勉強をしている中で、上手く日本語を伝えることができずに、もどかしい思いを感じることが多々ありました。それで一念発起して、以前から関心のありました420時間日本語教師養成講座を受講することにしました。同時に、日本語教育の理論面も身につけたいと考え、日本語教育能力検定試験も受験することに。
2022年12月からアルファ国際学院に入学し、半年間は自宅での通信講座を受講。残り半年はスクーリングで講義に通いました。スクーリングは、毎週土曜日の朝から夕方まであり、スケジュールのやりくりが大変でしたが、模擬授業や現役の大学生(ベトナムの大学)とのオンラインでの実習授業など実践的で役に立つプログラムだと感じました。教案の作成や「みんなの日本語」を用いての文型導入→基本練習→応用練習の一連の授業法などを学び、マンツーマン方式の西和夜中での勉強にも参考になることが多いと実感しました。
日本語教育能力検定試験は、2023年11月に受験。日本語教師養成講座のクラスメイトも検定試験の受験勉強をされており、色々と情報交換ができたこと、また何より同じ目標に向けて努力されている方の存在はとても刺激になり、何とか合格することができました。
西和夜中に通って来られる皆さんの、今ここで何とか頑張ろう、必死で生きようとして努力されている姿には本当に頭が下がります。それぞれのひたむきな姿勢に心打たれますし、リスペクトを感じます。同じ時代を同じ地域で生きる隣人として、自分が出来ることをお手伝いさせて頂ければと思い、西和夜中に携わらせて頂いています。 420時間日本語教師養成講座と日本語教育能力検定試験で学んだことを活かして、西和自主夜間中学に来られる皆さんに、少しでも分かりやすく日本語をプレゼントできればと思います。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
力をくれた夜中との出会い
2024年年7月23日 せいわ夜中1学期最終日でのご挨拶
こんにちは。スタッフの野村です。
大変残念ではあるのですが、最近 仕事と家の用事が増え、毎週夜間中学に足を運ぶのが難しくなってきてしまいました。今後は皆さまとお会いできる日が少なくなると思いますので、少しお話を聞いていただければと思いこのような時間を取らせていただきました。ありがとうございます。
私が西大和自主夜間中学に来たきっかけは、昨年6月に教会を通してボランティアの募集を拝見したことです。その一昨年前頃から日本語指導に興味を持っていたため勉強になりそうということ、また17歳の娘がフィジーに短期ボランティアに行くことになり少しでも参考になればということもあり思い切って飛び込んでみました。
実を言いますとその前の数年間、私は愛犬の介護で睡眠不足が続いたり、コロナ禍での不安、シングルマザーで子供とペットを私が養わなければというプレッシャーなどで、心身ともにきつい日々を過ごしていました。自分に自信も失っていました。なんとか自分を変えなければと思い立ち、今までの習慣を少しずつ変えていったその1年後くらいに夜間中学と出会うことができました。
はじめてのボランティアで、何をしてどんなふうに力を注げばいいんだろうと思いましたが、参加してみると、生徒の皆さんは積極的な方が多く、スタッフの方々は「人に与える」気持ちが大きく、また良い教育に関心をもっておられ、とても良い空気感が漂っていて私もその中に居られることに幸せを感じました。また私が受け持たせていただいた生徒のかおりちゃんは、明るくて物怖じしない感じだったので、私も自然と心を開くことができました。
そのようなことがきっかけとなり、再び週5日で仕事する運びとなりました。この1年で感じたボランティアの良さは、何といっても人との出会いです。スタッフの方々は様々な分野でキャリアを持っていらっしゃるので刺激にも勉強になり感謝しています。かおりちゃんとそのご家族始め生徒の方々からは、色々な国のことなどを教えていただけたことも勉強になり楽しかったです。また笑顔で挨拶すること、笑うこと、感謝されることは、目には見えない、心へのプレゼントだと感じます。
私自身は経済的な事情もありしばらくは仕事優先の生活になってしまいますが、参加できる日はぜひ行かせていただきたいと思っています。私の話が、ボランティアを迷われている方の背中を押すひとつの力になればと思っています。
ご清聴、そしてお世話になり、ありがとうございました。
注:野村さんは夜中を退会ではなく、一時休会となります。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「35年目のラブレター」を読んで
山上真也
2024年8月2日
本の紹介:「35年目のラブレター」(著者:小倉孝保)は奈良県の夜間中学で読み書きを習い、結婚後35年にして妻に初めてラブレターを書いたという人生を記録したノンフィクションです。文字を習う機会を逸し、それを隠して生きてきた困難な人生を変えたものは何かを問う本です。
人の悩みや苦しみというのは、その多くが人間関係から生まれてくるものだということ。そして、生きがいや喜びもまた、人間関係から生まれるということをあらためて感じます。本当に困り果てた時、絶望感に苛まれた時に、たった一人でも誰か話せる人がいることで人は救われる。誰かの関心があればこそ、人は生きていけるのだとの思いを強くしました。西畑さんにも、人生の節目節目でそういった方々との出会いがあったのだと想像します。
西和夜間中学に来られる外国にルーツを持つ方々は「日本語を話せない苦しみ、伝わらない辛さ」を少なからず感じておられるでしょう。西和夜間中学は、困難を抱える人に大いに関心のある場所だと思いますし、「人とのつながり」に出会える場所だと思います。そして、それはとても意義のあることだと考えます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
言葉からコミュニケーションを目指して
松村秀子
20240703
西和のホームページが完成し、それを見て訪れる生徒さんが増えています。私も夜間中学の事がより理解できる様になりました。
長年ボランティアとして夜間中学に参加し、週に1、2回ですが多くの生徒さんと関わっています。皆、日本語を覚えて会話を楽しんだり、不便を感じない生活を送りたい気持ちは同じです。そのため、できるだけ気持ちに寄り添い丁寧に接することを心がけています。「みんなの日本語」(テキスト)で学習を終えたら、重要な一句を繰り返し練習します。次の週には言葉の数も増え、表現力も向上します。生徒さんが「楽しかった」と話すと、私も嬉しくなります。
読み書きができる生徒さんには、文字で覚えるだけでなく、音で覚える方法もアドバイスしています。幼児が言葉を話せるようになるのは、大人の言葉を聴いて真似るからであることを説明すると生徒さんも納得してくれます。以前、ある生徒さんから「 '大丈夫' や '良い' の使い方が難しい」と質問がありました。日本語では主語が省略されることや、イエスかノーかが曖昧になることがあります。例を挙げて説明していますが、日常的に日本語でのコミュニケーションが不足していると感じます。
生徒さんが社会に馴染むためには、言葉だけでなく、習慣の違いを理解し、相手の表情、声の抑揚や仕草などを観察することも大切であることを伝えています。生徒さんたちは、日本人の友達を作ることが難しく日本語を使う機会も少ないと言います。担当している生徒さんだけでなく、ご縁あって夜間中学に来てくれた生徒の皆さんにも声をかけたいと思っています。
ホームページが必要な方の目に留まり、更にご縁がつながりますように。制作に尽力している木村さんと高柳さん、これからもよろしくお願いします。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
魚を採る方法を学ぶ
スタッフ:木村暁
20240627
ある日の授業が始まろうという、生徒さんたちが三々五々集まり始めたとき、久しぶりに生徒のフランス人のFさんの顔があった。彼をサポートしていたスタッフは一か月ぐらい前に辞めたので彼もしばらく姿を見せなかったのだ。思いがけなくその日は手の空いていた私がお相手をすることになった。彼は以前のスタッフとかなり流暢な日本語を話し、受け答えをすることができる生徒さんであったので、どういう動機で夜間中学に来るようになったのか、ということから話を始めた。
彼は飲食関係の会社で仕事をしているのだが、雇用契約書やオファーなどを含む日本語ビジネス文書を読み、あるいは作成することができるようになりたい、という。それも単に文書を理解できるだけでなく、例えば契約書のどのあたりの部分があいまいであるか(彼はそれを「胡散臭い部分」と言い直した)、を指摘するだけの力量を目指しているという。それには漢字の理解が必須であると思って夜中に来たが、彼にとって今の夜中のサポートは少なからずフラストレーションを感じるものであることが、言葉の端々に感じられた。彼のはっきりした目的に沿った日本語ではなく、どちらかと言えば夜中のサポートが日本語検定をパスするための、幅広い一般的な日本語学習に傾いていることがその理由なのだ(もっともそれは雇用主が求める要求であるからであるのだが)。
彼は日常的に日本語で話すこと、聞くことにほぼ不自由がないため、読み書きに困難が生じると、それを一つずつ会得しようとするより、彼にとって楽なところに逃避してしまう、つまり直接日本人の誰かと話をする中で、なんとなくその意味するとこを感じ取ってしまうことで済ませてしまうのである。彼はその処世が安易であり、それを誰かにはっきりと指摘される必要があると自覚していて、夜中にそのことを期待しているのだという。
こんな話を聞きながら、私自身が30歳半ばで日本企業から外資系に転職した経験を話した。40年前、転職はまだ白い目で見られていた時代である。東京で買った家をわずか1年で手放して関西に移住し、食品業界から医薬品業界へと転職することは人生の大きなかけであった。しかも外資系であるから英語の力は必須である。しかし、大学受験のために勉強した英語は20年近くお蔵入りしていた。私は二つのことに絞った。一つは自分がこれから生きていこうとする専門領域の言葉(日本語、英語とも)を優先して習得すること、二つ目にはNHKのラジオ講座の続基礎英語からやり直すことであった。
Fさんは私のこうした経験を聴いて、フランスでは「貧しい人に魚を差し出すのではなく、魚を採る方法を教える」という諺があると話してくれた。つまり生きる術を学ぶことが最も重要なことであると。
今の夜中には外国人技能労働者の生徒さんが増え続けている。彼らは来日するために莫大な費用が必要である。彼らは多額の借金をすることで、後にはたやすく後戻りできない状況にある。私は自分の転職の経験に重ねてそれを、「背水の陣」というと、Fさんはフランスの表現では「壁を背にする」と教えてくれた。外国からの技能労働者はとてつもなく大きな「壁を背にして」日本で生き延びようとしているのだが、私たちはそれがどれほどのものか想像できていないかもしれない。
日本が求める技能の職種はさらに多種多様になりつつある。それらに個別に応える可能性を持つのは自主夜中の強みであろう。彼らが生きていくための学習を優先することは、これからの夜中の課題になるのだろうと、Fさんから教えられた。
彼の話には続きがある。日本語を良く習得することで、他人(日本人、とりわけ彼の奥様や仕事仲間)への依存を減らすことができ、その分多くの自己責任を持つことができる、そのための出発点として漢字交じりの日本語を学びたいという。学ぶことの動機の持つ意味を考えさせられる機会であった。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
伝えたい:よりよく生きるための勉強を
スタッフ:吉岡泰次郎
2024年6月14日
西和自主夜間中学で学ぶ生徒さんは、海外ルーツの方が多い。技能実習生として、また専門家ビザを持たれて、また日系人としての定住者ビザを持たれて、いろいろな現場で働かれている。お仕事の内容をお聞きすると、ほとんど日本の若者たちが希望しない、いわゆる3Kの現場での仕事に従事されている事が多い。
最近、ある青年に出会った。母国の大学で専門知識を学ばれて、日本に来られたが、真夏の屋外の電気製品取り付け工事、換気の無い異臭のきつい印刷業務の経験を経て、現在は金属部品の機械加工の会社で働かれている。強い洗浄剤で皮膚をやられたり、ずっと残業が無くなって収入も減り、奥さんも働かれているが体調を崩されているという。家族を守るために、どうしたらよいかと模索しておられた。私は会社員時代の先輩に相談した。彼は、一つの会社を紹介してくれた。うまくコンタクト出来て面接の機会を与えていただいた。素晴らしい会社だと思った。海外にも工場があり、海外からの人も働いておられた。しかし、面接では、彼は自分をアピールが出来なかった。面接の練習をしておけばと悔やまれた。面接後、希望の年収を尋ねられ彼は自分の希望額を連絡された。決して高い額ではなかった。しかし結果は不採用だった。
私は耐えて頑張れ、と励ますと同時に現在の自分の置かれた職場の中で、一生懸命勉強して、考え実行できる技術者として、リーダーとして、いろいろな課題を改善提案し実践して、取り組んだ成果をアピールできるようになってほしい。そうすれば、必ず道は開けるからと説明した。
私事ではあるが、私は金型の技術者です。大手の電気製品メーカーで働いていました。47歳のころ「開発途上国の製造会社で働く若い人達に、金型メンテナンスを中心に、金型技術を指導する出前金型スクールの先生になってほしい。」と命じられた。当時、多くの海外の工場では、「いわれた事しかしない。」「失敗しても言い訳ばかり」という人が多いと聞いていた。そして受け身の人達を、積極的に自分たちの工場の問題解決に挑戦する技術者に育てる事に挑戦した。私が20年間に亘って取り組んだ人材の能力開発、リーダーシップの育成を通じて得た「理想の指導者のいない環境でも、自分たちが自分たちの先生になって、自分たちの能力を向上できる」方法を、西和自主夜間中学で、日本語学習と共に、マンツーマンで伝授したいと夢を持っている。必要な専門知識や手書き製図実習と一緒に、試行を始めたいと思う。誰からも奪われない人生の本当の宝物は、①親から与えられた名前 ②問題解決のために考える力 ③他者に評価される技能スキルの三つであり、この3つを磨き上げる事が、最も大切だと思う。これを伝えたい。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
夜中と生徒さんから学ぶ
スタッフ:松村國隆
2024年年6月10日
昨年の秋(2023年9月12日)から、西和自主夜間中学に参加しています。最初は、二人のベトナム人青年を相手に日本語学習のお手伝いをしていましたが、一か月を過ぎた頃に一人になりました。彼の名前はソン・ホアン・チュン君です。ハノイ近郊出身の彼は昨年の春に来日し、現在は、技能実習生として、近在の職場で働いています。彼の勤務時間の関係上、隔週の火曜日と木曜日の出席になっています。日本語学習のある週には、必ず携帯電話で連絡を取り合っています。
夜中という初めての経験
わたしは1970年から2014年までの足掛け45年間、専らドイツ語およびドイツ・オーストリアの文学や文化を教えてきましたので、ドイツ語圏からの留学生たちを受け入れる際に生活面でサポートしたことはありましたが、正式に、しかもアジア語圏からの日本語学習者のサポートをするのは初めての体験です。
毎回、新しい発見の連続に一喜一憂しながら、また試行錯誤しながらマンツーマン学習に臨んでいます。まずは、ソン君と挨拶を交わし、二週間の生活を振り返って会話することから始まります。そのあと、前回の復習のために、予め作成してきた問題に取り組んでもらいます。復習、とりわけ反復練習はとても大事なことです。なぜかと言いますと、そこには様々な気づきがあるからです。復習問題の作成は目下18回を数えています。それが終わりますと、夜間中学の事務局で用意された「日本語能力試験N5直前対策ドリル&模試 文字・語彙・文法」をテキストに日本語学習を進めます。ちょうど「Part2 実践ドリル 文法」の第12回を終了したところです。
生徒さんに学ぶ
スマホの翻訳機能を利用しています。日本語からベトナム語へ、ベトナム語から日本語への翻訳が可能になり、大いに助かっています。ときどき横道にそれることもあり、スマホを見ながらベトナムや日本の料理を話題にすることもあり、地図を見てベトナムや日本の町や各地方の名前を確かめることもあります。できることなら、わたし自身がベトナム語を学習して、スマホを使わなくてすむ程度になりたいものです。でもCD付「ゼロからスタート ベトナム語」を買い求めたまではいいのですが、とくに発音と文字が難しいので、大きな壁にぶつかり、一向に進捗しません。まだXin Ciao!(「こんばんは」)とBan khoe khong?(「元気ですか?」)と Tam biet, tam biet(「さよなら、さよなら」)だけが、かろうじて口から出てくるベトナム語です。
緩やかな居場所のよさ
わずか半年間の体験ではありますが、西和自主夜間中学のいいところは、マンツーマン形式の学習サポート体制が徹底していることです。そこには自ずと相互の責任感が生まれますし、相互の信頼感も湧いてきます。もう一つ気づいた点は、緩やかな体制であることです。遅れて来てもいいし、早く切り上げてもいい。強制的でないのは、双方にとって負担が軽減される、ありがたい体制だと思っています。
共生するという理想とむつかしさ
話は変わりますが、カトリック京都教区の奈良ブロックには国際協力委員会という組織があります。西大和カトリックセンターでは、吉岡さんがその任を引き受けてくださっています。5月11日の同委員会にわたしは吉岡さんの代理で出席しました。その際、一人の委員から、「日本で働いておられる外国人の方々に対するわたしたち日本人の認識を根本的に改めることが問われている」との指摘がありました。日本ではこれからますます少子化が進むなか、世界中から労働者を受け入れる際に、人権思想が未だ十分に根付いていないなかで、どのように「共生する(共に生きる)」かが日本人にとって最重要な課題になるでしょう。この会の委員長である奈良教会の田中さんが、西和自主夜間中学の活動に関心をもたれ、先週の木曜日に参観されたことも申し添えておきます。
さらに、6月10日から実施される新しい「入国管理法」について、昨夜、Zoomでの学習会が行われました。わたしはそれに参加し、その実態を具に知らされました。とくに、大学を卒業するまで、家族全員が仮放免の状態にあった女性の報告が印象的でした。父親は不法滞在のために、すでにペルーに強制送還されている状態でしたが、最近ようやく彼女と弟の二人に特別滞在許可が下りました。しかし母親は仮放免のままで、子供たちが自立できるようになったのだからとの理由で、入管から帰国を促されているそうです。
せいわ夜中のルーツ
西大和カトリックセンターでは、1990 年代にマリスト会のオヘール神父、吉岡さん夫妻等が中心になり、それに斑鳩町議会議員であった山本直子さんの協力も得て、当時、日本に来て働いていた教会内外のペルー人たちのために、保証人バンク制度を立ち上げられました。ずいぶん早い時期の外国人労働者のための救援活動でした。当時わたしは別の教会に所属していましたので、吉岡夫人の友達であった妻からその活動をよく聞かされていました。西和自主夜間中学の源をたどりますと、そこに行き着くことを知り、不思議な縁を感じている次第です。
夜中を通じた得難い学び
西和自主夜間中学にボランティアとして参加させていただくようになってから、日本で働いておられる外国人の方々への関心が一層深まったように思います。その点で、ベトナムの青年ソン君の日本語学習のお手伝いをする機会が与えられたことに心から感謝しています。そして国際協力委員会の一委員の発言にありましたように、わたしたちはこうした方々に対して根本的に意識を変革するよう迫られている、そして「共生する(共に生きる)」とは何かを再考するよう促されている、そう思うこの頃です。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「現在の夜間中学運動の様子と今後」
2023年度第69回全国夜間中学校研究大会での報告から(抜粋)
「西和に夜間中学をつくる会」
事務局長・奈良県夜間中学連絡協議会代表
発表者:山本直子
せいわ夜間中学設立のいきさつ
夜間中学のある西和、ここは奈良県の中の北西部にあたる地域です。その地域に自主夜間中学を作りませんかと米田先生の提案を受け、1997年の1年余りをその準備に費やし、1998年の5月に県内で2番目の自主夜間中学として北葛城郡王寺町というところの中央公民館を会場として開校いたしました。その2年余り前には、私たちの先輩である吉野自主夜間中学が大淀町で開校しています。
母体となった奈良保証人バンク
当時、私は人口3万人に満たない生駒郡斑鳩町で町議会議員をしていました。1992年といえば、その頃急激に増加してきた外国人労働者がおり、私たちのような人口3万人に満たない町もその波に揉まれていました。当時は出稼ぎと言われて日本に定着することすら予測されなかった外国人労働者たちが経済的に安定をしていく中で、家族を伴って日本で生活をするようになってまいりました。それに伴って、日本で子どもたちが保育園に行く、小学校に行くということが顕著になってきました。生活としての日本語に加え、学習言語としての日本語の習得が、私たち、彼らの生活支援をしている活動団体である奈良保証人バンクとしては喫緊の課題となったわけです。1997年準備会の1年間は、私が夜間中学を知る年月となりました。そのような経過を辿って私たちは西和自主夜間中学を王寺町に 1998年に設立することになりました。
せいわ夜間中学の特徴
当初から西和自主夜間中学は、非常に特徴的な自主夜間中学として出発をすることになります。すなわち、生徒さんの8割以上が外国人労働者とその家族の皆さんであること。そして今日的な課題でいえば、その中でも、学齢期の小学生・中学生・高校生で外国にルーツのある子どもさんたちが一緒に勉強しているという特徴があります。国籍で分けると、必ずしもその生徒さんたちは外国籍ではありません。日本国籍を持っていらっしゃる方も半数以上います。しかし、ご家庭での母語が、例えばスペイン語と中国語のご夫婦の間に生まれた子どもさんであれば、生まれたときからお父さんやお母さんが話す家庭での言葉、拙い日本語の中で育つわけです。なので、外国にルーツがある子どもさんも一緒に私たちの自主夜間中学で学んでいて、そして皆、日本で生活をするために日本語の習得と教科の学習をし、そして高校進学ということで頑張って学習しています。そういった特徴がある自主夜間中学として出発をいたしましたが、私たちの自主夜間中学は勉強をする、日本語を習得するという場所だけではどうもなかったようです。それは、彼らが抱えている背景、彼らが日本で働いていくために必要な日本語を学ぶということだけではなく、自分たちのアイデンティティの保持をしていく、その居場所としても私たちの夜間中学はとても大切な意味を持っているのだということが26年間の活動の中ではっきりとしてまいりました。
せいわ自主夜中を支援する人々、団体
さて、西和自主夜間中学は、その発足から26年を迎えました。現在は、王寺町のご事情で王寺町地域交流センターというところに学校の場所を移し、毎週火曜日と木曜日、午後6時から9時に開校しています。現在は9カ国30人の方が生徒さんとして在籍をしていらっしゃいます。マンツーマンでの学びが中心です。その生徒さんたちにマンツーマンで学びを保障していこうとすると、それに相当する数以上のスタッフの皆さんが必要になります。私たちは26年間の中で、地域の皆さんや先ほどからお話のあった奈良県夜間中学連絡協議会の全面的な支援の中で、たくさんの地域の皆さんにスタッフとして参加をしていただいています。これはとても地域の力として自慢のできることだと思います。
生徒さんの入れ替わりはありますが、スタッフの入れ替わりは西和に関して言うと非常に少ないです。長く、西和自主夜間中学に市民の皆さんがボランティアとしてお金を提供し、ご自身の能力を提供し、そして時間を提供して生徒さんたちに向き合ってくださっています。これによって私たちは26年間続いてきたのだというふうに思っています。これが地域の宝だというふうに思っています。私たちの学校では日本語という言葉の習得だけでは足らなくて現在では教科の指導も必要となってきていますし、日本語能力検定の N2,Nlといった高度な能力を必要としている生徒さんたちもいらっしゃるので、そういう指導ができる先生たちが必要となってきているのですが、そこの部分はかつて教員であった方、あるいは現場の教職員である方が担当してくださっています。
吉野自主夜中と宇陀自主夜中
奈良県には、あと二つの自主夜間中学、私たちの先輩の吉野自主夜間中学、それから、少し遅れて発足した宇陀自主夜間中学がありますが、それぞれ特徴のある自主夜間中学として地域に根付いています。吉野の自主夜間中学は、山間部の入口にありますけれども、林業や炭焼きやさまざまな基幹産業の下で必要とされている外国人労働者と家族の皆さんを地域でずっと支えながら学習を続けておられます。非常に地域に根付いた夜間中学として現在も活動中です。宇陀の自主夜間中学も非常に特徴のある学習をされています。現役の不登校生である学齢期の生徒さんたちを中心に、学校の現役の先生方が中心になって学習を支えていただいています。
自主の良さ
私の意見でしかないかもしれませんが、西和自主夜間中学全体としては、今すぐに公立化を必ずしもめざしてはいません。ただ、西和地域のいずれかに公立夜間中学を設置すること、あるいは設置されることは必要だと思っていて、歓迎をします。地域の日本語教室という冠を被せられても、私はそれぞれの地域に自主夜間中学があることについては大歓迎です。これまでの自主夜間中学26年間の経験の中で言えることは、自主夜間中学の営みこそが間違いなく公立の夜間中学の学びの裾野を広げている、という確信をもっています。
夜間中学を支える連絡協議会の運動
それでは、これからは奈良県の夜間中学連絡協議会について少しご紹介をしたいと思います。奈良県夜間中学連絡協議会は1992年に設立をされていて、現在では6つの夜間中学とそれぞれの「つくり育てる会」の全部で12の団体で構成をされています。そして、奈良県の公立の夜間中学はすべて自主夜間中学から出発をしています。私たちの協議会の性格については、全国的に誇れる組織だというふうに思っています。協議会であるという名称の通り、それぞれの夜間中学の運営方針を尊重しながら、私たちの活動の目的、すなわち夜間中学生の学ぶ環境をよくすること、そして通える範囲に夜間中学、自主夜間中学を増設するという夜間中学の増設運動という二つの活動目的のために必要な協議をしていく団体であることは間違いがありません。何よりの特徴は、公立 3校と自主3校が対等の立場で連携ができることです。
それは対等な形で教育委員会のチラシに掲載され、奈良県の所要なところにポスターとして掲示されています。この道筋を、先ほどの米田先生や私たちの先輩の奈良県の夜間中学の運動団体である奈良県夜間中学連絡協議会に関わる方々が作ってくださいました。このような目的をもって夜間中学を運動として支えている団体は、全国にも奈良県だけです。奈良県にある自主夜間中学は、あるいは奈良県にある公立の夜間中学は、全てその運動の中で生まれ、そして市民の皆さんに支えられて今日にいたっているというふうに私は思っています。奈良県夜間中学連絡協議会は、今この舞台で会合をもっていたような生徒さんたちの集まりである生徒会と一緒に、県の教育委員会と話し合いの場を長年重ねてまいりました。話し合いの場というふうに申し上げましたが、初めのころのことを振り返ると、私はとても話し合いの場というふうには思えなくて、まさに魂を入れた交渉というふうな感じの話し合いの場でした。そして、年ごとに要求書をまとめ上げて、その話し合いの場で教育委員会からの回答を求め奈良県夜間中学教育基本方針の策定を奈良県に求めてきた経緯があります。
2016年12月にいわゆる教育確保法が公布され、翌年から施行されることに触発されるような形で、2021年3月、「奈良県夜間において授業を行う中学校に関する基本方針」が教育委員会として策定されました。私たちの夜間中学、それは本来あってはならない学校、でも、とても必要とされている学校です。夜間中学についての県の基本方針や基本的な認識がようやく今明らかになったというのが、私の率直な感想です。本来私たち人が持っている教育を受ける権利を、これまで国や行政は保障してこなかった。その結果、全国にたくさんの未就学の生徒さんがおいでになります。長い間、国や行政はそのことを放置してきました。夜間中学に、ようやくたどり着いた一人ひとりの夜間中学生の背後に・背景に、その歴史はまざまざと刻まれているのです。だから、私たちは生徒さんから学びます。
作ればよいという政策は終わりにしたい
私たちは、夜間中学という箱物や入れ物を作ればという考え方では不十分だということを提起したいと思います。もちろん夜間中学のない地域に最低でも1校、夜間中学を設置するという考え方がいけないと言っているのではありません。でも、本当にそれぞれの生きている生徒さんたちがその中で幸せだと、学習できて勉強できて幸せだと思える夜間中学が作られなければならないというふうに思っています。これは、私たちの奈良県夜間中学連絡協議会の積み重ねの中で、手放しではできないということがはっきりわかってきました。支える会や市民の皆さんの力があって夜間中学は存続をしています。それぞれの地域で厳しい言葉も交えながら交渉を続けてきた。それは何よりも、今まで文字を奪われた、書くことを奪われた、それは外国人労働者の皆さんも一緒です。彼らが海を渡ってこなければならない相当な理由があって、そして、日本で低賃金と言われる3Kの現場で、日本の若者が働こうとしない「夜中の仕事」の現場で働いています。彼らに日本語は必要ないと思っている人たちが多いのです。彼らは機械のーコマのようにそこで働けばいいだけというふうに思って、今まで一度たりと人としての扱いを受けませんでした。
共生する人々としての政策を
彼らは外国人労働者としては日本に歓迎されました。しかし、家族を愛し、家族と共に暮らすという当たり前の基本的な人権が守られたことはありません。日本語を学ぶことを通してようやく彼らは人として認められるようになったのです。私は今、外国人労働者やその家族の皆さんが、日本語を学ぶ・知る機会を奪われている人たちだというふうに思っています。だから、自主夜間中学は彼らを受け入れています。だから、自主夜間中学は、彼らがご家族で一緒に生活している子どもさんの受け入れをしています。
国勢調査で明らかになったように、奈良県の義務教育不就学・未修了者の方々は、8,513人もいらっしゃいます。実際の数字は実はもっと多いと私は思っています。今、奈良県の6つの夜間中学で勉強できている生徒さんの数は本当にわずかです。それを考えると、まだまだ対応ができていないという現実があります。夜間中学、自主夜間中学はもっと地域に必要だということをこの場で訴えさせていただきます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
畑荒らしても子ども荒らすな
吉岡泰次郎2023年11月18日
尊敬している岐阜県の有機農業家の服部圭子さんのメッセージを以下にご紹介します。
…………………………………………………………………
農業関係の方なら、ピンとくるかもしれません。20年以上前の「現代農業」で紹介されていた名言です。あらためて調べてみたら、帯広の八千代中学校の地域の大人たちの3大名言のひとつとして載っていました。厳しい開拓民の中で生まれた名言なのでしょうか。
手が回らず畑を荒らして草ぼうぼうにしていても、また、やり直せるけれど、子どもは、日々育っていくから、子育てはやり直しがきかないという意味です。2番目の子どもが3歳のころだったか、2年間の電気ガスなし生活をした後だったか、この言葉に出会ったのがいつだったか定かではないのですが、この言葉には、勇気づけられました。
忙しい新規就農の農業生活の中でも、草がぼうぼうで、やることもいっぱいだけど何のためにいなかに暮らしていたかったのか?何を隠そう、子育ての為だった。子どもとの時間を中心に据えることは仕事より優先してもいいんだと、優先しなくてはいけないと教えてくれた言葉でした。
これ、
畑を仕事にかえてもいいです。子育てを、自分の体育てに変えてもいいです。育てるってのは、物ではできないのですよね。
いい食べ物だけではできないですよね。お金ではできないのですよね。お金中心主義や学歴中心主義や他人の評価中心主義に陥ってしまいがちの物差しが横行している渦から、子ども荒らすなが、
目覚めさせてくれた言葉だったことをあらためて思い出しました。
子育てに、言葉かけとスキンシップ整体を取り入れて、体をやわらかくあたたかくすることで、ママと子どもの幸せにしかなれない世界を伝えている、星野トチロー先生の自然育児学校に感動しています。
https://peraichi.com/landing_pages/view/sizenikujigakkkou/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
夜中から元気をもらって感謝です
こんにちは、野村 恵です。2023年11月15日
夜間中学のスタッフにさせていただき、約5カ月になりました。至らない点も多々ありますが、スタッフの皆様や担当のお子様、ご家族など、皆さま本当に暖かくて、心から感謝しています。
日本語を教えることに携わりたいと、軽い気持ちで始めましたが、毎回、元気を受け取り、いつのまにかとても満たされていることに気づきました。
そして、日本語を学ばれている皆さまの成長とともに、自分も学んでいけるといいなと思っています。これからも色々とお世話かけると思いますが、どうぞよろしくお願い致します。
ラベンダーに託した想い
吉岡泰次郎 2023年6月22日
先日の西和自主夜間中学の時に、ラベンダーの花を持って行きました。このラベンダーの花は、近畿地方の最北端の京丹後市の宇川地域にある海の見えるラベンダー畑の会の皆さんからのプレゼントです。
この地域は、大変厳しい自然環境の中にあり、過疎化が進み、唯一のスーパーも閉店になり、決して恵まれた状況ではありません。それでも、大阪から移住された一人の女性が、地元のお母さん達に、「自分たちの生活している場所に、誇りや夢や希望を持たなければ、誰が、この地域を発展させてくれるのだ」と呼びかけて、地元のお母さんたちと一緒に、荒れた土地を開墾して、ラベンダー畑を作ったのです。
でも、この女性は、自らトラクターを運転中に、トラクターごと転落されてお亡くなりになりました。お葬式は、お母さんたちの手作りでした。みんなで棺を持ってラベンダー畑の中を歩き周り、詩を朗読し、御詠歌を唱える葬式だったそうです。
この女性の意向は、地元の女性に受け継がれて、ラベンダー畑は、ずっと世話をされて毎年、6月になると素敵なラベンダーの花が咲き多くの人たちが、集うようになったのです。私は、丹後では、このお母さんたちのグループの応援をしています。耕運機で耕したり、草刈りをしています。西和自主夜間中学の話をすると、とても喜んで下さり、ラベンダーの花束を託してくれたのです。
宇川加工所のピンクのおばちゃんたち
京丹後に住み、地域の人びとを支える食の地域活動の紹介です。私たちせいわ自主夜中にラベンダーの花を贈ってくださった方々です。
(5) ピンクのおばちゃんがゆく(宇川加工所) - YouTube
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
始めの第一歩
スタッフ:鍵本幸子 2023年7月18日
笑顔であいさつ・自分流で、教室に入ると同時に「こんばんは」と明るい声と笑顔で挨拶を心がけるようにしています。
笑顔は、周りの人に伝染し、お互い自然な笑顔から教室の空気が和やかになり、ちょっとしたコミュニケーションが進んでいくことに繋がります。
さあ、今から楽しい学びとコミュニケーションの始まりです。
マイちゃんと木工のおもちゃ(支援者からの寄付です)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
生徒さんに感謝
西村和真:夜中を卒業するにあたって
夜中(やちゅー)が始まって以来今日まで20数年、いよいよ卒業となりました。ど~してこれまで長い間やってこれたんですか?と聞きたくなるでしょう?
お答えします。最初の頃は高齢者の⭕️⭕️さんと一緒に勉強していました。進捗状況は一歩進むと二歩下がり、二歩進むと三歩下がりでした。それってマイナスじゃないの?このままだとどんどん下がっていくよ~。でも⭕️⭕️さんはあきらめません。下がっても下がっても勉強を続けるんです。何度でも何度でも何度でも何度でも(もーうドリカム状態です)。
私はと言うと、自分の会社もたたんで、離婚もし、ドン底でした。そんな私を救ったのは、なんと⭕️⭕️さんでした。教えてる様で、教えられていた。それが力となって今までこれたのだと思います。感謝感謝です。
長い間お疲れさまでした。またの出番をお待ちしております(事務局員&スタッフ一同)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
第26回総会のメインイベント
生徒さんたちの想いの発表
藤本ラビアさん
(香芝高校入学)
皆さんこんばんは。夜間中学に通っていた藤本ラビアです。ここには父が日本語を勉強しに来ており、 その紹介で私も勉強しに来ました。 もう5、6年通っているんですが、私の方が先に卒業しました。私は、(夜間中学に)日本語を勉強しに来たわけではないんですが、主に数学を丸山先生に約1年半教えてもらいました。
最後の方には英語も教えてもらい、 皆さんのおかげで私は香芝高校に入ることができました。ここはお菓子を用意してくれたり、お楽しみ会をしてくれたり、夜間中学でお友達もできました。 皆さんとても親切です。また顔出しに来ますのでよろしくお願いします。 丸山先生、私の父をビシバシ鍛えてください。
……………………………………………………………………
ウェンウェンさん
奈良県立法隆寺国際高校入学
(山本事務局長がインタビュー)
(山本)ウェンウェンさんにはインタビューをします。まず、どこの高校に入学したのか教えてください。
(ウェンウェン)えっと、法隆寺国際高校に入学しました。
(山本)今、学校は楽しいですか。
(ウェンウェン)学校はめっちゃ楽しい。めっちゃ楽しいですよ。友達もいっぱいできて。え。さっき遊び終わって帰ってきたばかりです。
(山本)遊びに夢中になって、ここの時間も忘れるぐらい一生懸命遊びましたが、部活はどうですか。
(ウェンウェン)あの、マネージャーするかまだ考えてます。
(山本)わかりました。最後にもう1つです。 お母さんも一緒に勉強してますよね。はい。あのー、お母さん、お仕事して、で、勉強もして、ウェインたちの面倒も見て、大変やと思うけれども、 ご家族に対して何か思ってることはありますか。
(ウェンウェン)いつもありがとうございました。
……………………………………………………………….
ダンロップ嵐くん
奈良県立国際高校入学
担任原田先生は、国語の漢字を教えてくれた他、先生の担当科目の社会を見てくれたりしました。私がF1や車に興味があるので、よくF1についての記事などをインターネットから印刷して持って来てくれて一緒に読んだりしていました。他にも先生といろいろ話をしたり、とても楽しく日本語の勉強をしていました。
高校受験の時も、夜中の先生たちがいろいろサポートしてくれました。いつも自分のことをしてくれたり、とても思いやりのある先生でした。学期の最後の日に全体集会があるのですが、生徒みんなでゲームをしたり歌を歌ったり楽しかったです。今までありがとうございました。
…………………………………………………………………….
リンさん(原文ママ)
皆さん、こんばんは。私はリンと申します。ベトナムから来ました。宜 しくお願い致します。 10 年ぐらい前、縫製の実習生として日本に来ました。その時、日本語 はまだ下手なので生活に困ることがたくさんありました。3 年後、帰国 して一生懸命日本語を勉強して、ベトナムでの日本語能力試験の N3 に 合格出来ました。結婚してから、2018 年に娘を出産して、2019 年夫は 技術ビザを取って日本に来ました。2021 年 9 月に私と娘は呼び寄せさ れて、日本に来ました。帰国してから、日本に戻りたかったです。日本は綺麗だし、安全だし、食べ物も美味しいし、日本人はとても熱心で住 みやすいから、今度日本に戻ることが出来て、とても嬉しかったです。
仕事しながら、娘を育てたり、保育所に送迎したり、病院に連れて行っ たり、N3 を持っていますが、日本人が何を言うか、分からない時もあ って、大変でした。しかし、日本に来たら、いい人にたくさん出会っ て、色々なことを手伝ってくれました。保育所の先生たちはとても親切 で、熱心です。日本に来る前に、娘のマイは日本語が全然分からなかっ たが、先生は優しくて少しずつ案内してくれて、安心して、預けていま す。マイは保育所が大好きです。私は迎えに行くと、帰りたくないと、 泣きました。日本に来て 1 年間ぐらいたって、娘は先生と友達から日本 語を習ってだんだん日本語をよくしゃべれるよになっりました。そして お友達がたくさん出来ました。 今は毎日楽しく遊んでいます。
マイは日本の食事なんでも食べれます。 保育所の給食は全然問題がないです。マイは家で親とベトナム語で話し て、英語も勉強しています。来年の 4 月から小学校に入ります。楽しみ です。 私も今年の 2 月に日本の運転免許が取れました。何回も試験に落ちて、 何回も辞めたいと思いましたが、子供のために、特に寒い日、雪が降る 日、雨の日もマイを送迎しないといけないと思って自分ながらよく頑張 って、やっと合格出来ました。とても嬉しかったです。
今から、暖かくなるので、畑で色んな野菜を植えることが出来ます。市 役所から 50平方メートル の畑借りて、日本の野菜とベトナムの野菜も植えまし た。畑にはお水、駐車場、お手洗いがないです。家から水を持っていた り、雨水をためたり、ちょっと大変ですが、畑は無料です。空心菜、つ るむらさき、なす、カボチャ、オクラなどを作りました。時々失敗があ りましたが、とても楽しいです。 今、毎日頑張って日本語を勉強しています。N2を受験したいと思いま す。漢字は一番難しいですが、勉強は好きです。頑張りたいと思いま す。毎週の火曜日、夜間中学に娘と一緒に来て、先生と勉強していま す。先生たちは熱心だし、優しいです。日本語を習ったり、生活で何か 分からないことがあったら説明してくれます。 日本に来てから、色々親切な人に出会って、色々なことを手伝ってもら いました。ありがたいです。 皆さん、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願い致し ます
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ミャンマーと入管と人権
吉岡泰次郎 2023年2月8日
皆さんこんばんは。
フェイスブックの友達からの投稿を紹介します。長すぎて自分でもイヤになるんですが、今回はとくに長いです。でも、日本の将来にかかわることだと思っているので読んでほしいです。よかったらシェアしてください。
………………………………………………………………………………………………
数年前からお付き合いのある30代のミャンマー人の青年がいます。単身で日本に働きに来ています。在留資格は、難民法により、国籍を有するもしくは常居所を有している国において生じた特別な事情により、日本に在留する者が報酬を受ける活動を許された「特定活動」というもので、1年ごとのビザの更新が必要な方です。年末に会ったときに、年末年始はひとりで過ごすと言うので「おせち料理をつくるから1月1日に食べに来ない?」と誘いました。しかし元旦に連絡してみても返事がない。ま、いっか。と思っていたら2日に電話がかかってきて「みかんをあげたいのですが、いまから行ってもいいですか?」。自転車にみかんひと箱詰んでやってきました。夫と息子が床にべったり寝そべっているリビングでおしゃべりしつつおせちを取り分けて包み、元旦につくった練り切りや、みかんじゃない果物とかをお返しにお裾分けしました。そしたら、10日後くらいに連絡がきて「わたしの民族の料理を食べますか?」と。
彼は料理はできないと聞いていました。訊けば、妹さんがいま日本に来ていて彼女がつくってくれるのだと。
2年位前かな、ミャンマー料理をしらべてつくってみて、彼に差し上げたことがあります。ミャンマー料理では納豆のような発酵した大豆を使うというのを知って自家製納豆を使って何品かつくりました。彼はよろこんでくれましたが、でも自分は普段あまりミャンマー料理は食べない、自分たちは山の民族で、ビルマ人と食べているものが違う、と言っていました。ミャンマーは多民族国家なので、まあそうなんだろうなあとそのときは思っただけでした。
ここは東京なのでミャンマーのコミュニティがあるのもわたしは知っています。お正月はひとりで過ごすと言っていたときに、高田馬場にはミャンマーのひとたちが大勢いるでしょう?お友だちはそこにはいないの?と訊くと、あそこには行きません、と。ミャンマー動乱のニュースを知ったときには、ご家族はみなさん無事なのだろうか、とても大変ですね…という話をすると、お母さんと妹はタイに避難した、それに自分たちの民族は長い間、もう100年以上ビルマ(ミャンマー)政府とは闘ってきた、いまに始まったことではない、というようなことを言っていました。彼はまだ日本語をそんなに使えず、英語と日本語で話すのだけど、細かい単語などは私も理解できずにいました。彼の民族を「キン簇」と教えてもらったと思っていたのだけど、彼はミャンマー語で「カイン簇」と言っており、それは日本だと(というか英語表記をカタカナにしたのが)「カレン族」と表記されるのだということが、この料理をいただいてミャンマーの地図を見ながら彼の故郷の話を聞いてやっと分かったのでした。
妹さんが滞在されている間にカレン族のデザートや、タイ料理にも影響を受けたかもしれないというパパイヤと海鮮の料理なども持ってきてくれました。わたしはお返しにパンを焼いたり、コリアン料理をつくって手渡しました。妹さん、とにかく料理が好きなのだという。わたしと似てるね(笑)わたしは民族衣装がとても好きなので、彼の民族衣装についても訊いてみたんです。すると満面の笑みになって、スマホでたくさんの画像を見せてくれました。マネキンが着ている民族衣装を指して「どの色が好きですか?Red?Black?」と訊かれて、紺色のがとても素敵で「これがとてもきれい」と指さすと「ほかにもありますよ、これは私の80歳のおばあさんです」と見せてくれた写真が衝撃でした。鮮やかなピンクの民族衣装に身を包んだ彼の祖母は、ゴツい機関銃を手にしていたのです。おばあさまも戦闘に立ってるの…?
80歳の女性が機関銃を手に戦闘に立つという現実。遅まきながら、わたしはカレン族について書かれた本を読み始めました。たかだか10冊くらいの本を読んで、ひとつの民族について「分かった」などと傲慢なことを言うつもりはありません。在日コリアンの歴史についてたった1冊の新書を読んで「分かった」みたいなことを言うひとに心底むかついたことがあります。わたしたちの100年以上の苦難の歴史を、1時間もあれば読める新書1冊で理解できたと? なんて厚顔無恥なんだ。自分はそうはありたくはない。それでも、これらを読んで、いままで彼から聴いた話のいくつかが少しだけ理解できたような気がします。読んだ本の著者はすべて日本人ですが、年代も性別もさまざまで、文化人類学者3名、ジャーナリスト3名、難民キャンプのボランティア、キリスト教徒の医療者(医療人類学という研究分野の存在をはじめて知りました)、国連職員、ノンフィクションライター。読んでいて、いままで全く知らなかったカレン族という民族についての知識を得ながら、同時に思うのはそれぞれの著者がどのような契機や思いで、カレン族やミャンマーや難民キャンプを研究や取材対象としたのか、ということでした。
たとえば、飯島茂の「祖霊の世界」という本は50年も前に出版された書籍です。情報としては古くもあるのですが、英緬戦争において、カレン族がイギリス側についてビルマ政府と戦ったこと、それには民族独立運動が背景にあり、だからもちろん日本軍とも敵対したわけだけど、日本もイギリスもビルマを去った後には政府からはますます迫害を受けて現在に至ることなども知りました。飯島氏の専門領域は文化人類学なので、それこそ村落構成や祭礼、信仰について、父系でも母系でもなく双系社会だということ、でも祭礼は母系が主導…だとか(それはわたしの感覚から言えばほぼ母系社会)、とても興味深く読んだのですが、飯島氏は1932年生まれ、つまり学徒として日本の敗戦を迎えている。経歴を見ると京都大学で法学博士号を取得しているのに、なぜ社会学者になり、ミャンマーとタイの少数民族を研究対象としたのか。
全編読み終えて、あとがきにある「日本人のアジアに対する浅薄な認識がわが国民の運命に重大な影響を与えた」「わが国で一般的に受け入れられているアジア観の多くは、都市から地方を眺め、上部から下部を俯瞰して形成されたものである。そこでわれわれ社会人類学(または文化人類学)を研究する者は、その視線の方向を逆に向け、アジアの山間の僻村からタイ国を眺め、アジアを見つめ、そして、われわれの日本を考えようとするものである」「いまやわれわれ日本人が早急にしなければならないのは、戦後二十数年にわたるわれわれの歩みと、それに連なるアジア進出の総決算である。とりわけ、それらの現実の底辺に横たわるひずみから目をそらすことができない以上、たとえわれわれの意見が社会人類学というわが国の”少数民族(マイノリティ)”の少数意見であるとはいっても、そして、それがどんな一般的風潮に逆らうように見えても、われわれは飽くことなく、地道に訴え続けなければならないと思う」といった文章を読んで、得心がいきました。
学問の根底にはヒューマニズムがないと成立しないとわたしは考えています。でも、いまはどうなのか。わたしが大学に心底うんざりしたのもその点です。今回読んだ本のなかで、いちばん共感をもって読んだのが黒岩揺光の「国境に宿る魂」で、巻末に記された経歴を見ると、1981年に新潟で生まれた黒岩氏は、アメリカ留学なども経て、ユトレヒト大学で「移民、民族、多文化」修士課程を修了し、毎日新聞社の記者となり、執筆時は国連難民高等弁務官事務所勤務で、ケニアで若者の支援をしているということだったのだけど、あまりにも気になって調べてみたら、なんとそれも辞めて予想もしない展開になっていました(ご興味のある方、ぜひ調べてみてください)。この本のなかでユトレヒト大学での経験も記されているのだけど「(…)自己満足な知識に執着する教授達。そもそも移民学コースの教授なのに、オランダに何十万といる移民と友人付きあいをしているような教授は一人もいない」というくだりでは、ほんと、「学問っていったいなんのためにあるの?」と、この数年わたしが感じてきたことを代弁してもらったような気持ちになりました。どの本にも著者一人ひとりの背景を感じたし、本など著さないけれど地道に現場で活動している方たちはもっと大勢いるわけです。その方たち、一人ひとりの背景も含めてどっと迫ってくるものを感じています。
これらの本を読む前に昨年末にターハル・ベン・ジェルーンの「おとなは子どもにテロをどう伝えればよいのか」という本を読んでいて、読みながらモヤモヤが解消されず、結局現時点ではわたしにはテロとレジスタンスの明確な線引きができない、という暫定的な結論に至ったのですが、カレン族についての本を読んでもその考えはますますつよくなるばかりです。世界はひとつの物差しで測ることはできない。たしはカレン人の彼に出会わなければ、ミャンマー大変だな…とは思っても、こうしたことを知ろうともしなかっただろうなと反省します。不明を恥じるってこういうことだなと思う。
ミャンマーという国家で起きていることを国際ニュース(それは先進国のメディアが流しているものでしかない)で知るのみだったのだけど、カレン人をはじめとした少数民族からしてみたら、アウンサンスーチーと軍事政権だって、所詮ビルマ民族という多数派の権力争いにしか映らないのだろう。
彼らは、1世紀以上も国家から迫害され、虐殺され、闘い続けている。彼の父は数あるカレン族の民族独立組織(ここでは詳述しないけど、カレン族も宗教や思想や育った環境など一つひとつとっても、じつに多様な民族です)のKNU(カレン民族同盟)に属しているのだという。知り合って4年ほど経ちますが、わたしの口から「KNU」などという言葉が出るとは思ってもいなかったようです。彼は最近引っ越しをして、いままで外国人ばかりが住んでいるアパートだったけど、いまのアパートはたくさん部屋があるけど外国人はわたしだけです、と得意げに話していた。大家さんにもみかんを届けたら、こんなことをしてくれる住人はいないよ、と喜んでいた、とうれしそうに話していました。わたしにはその気持ちが分かります。
在日コリアンは日本に生まれて育って日本人と同じように日本語を使えて(わたしなんて大半の日本人より日本語上手だと思うけどね)、日本人と同じように納税していても「外国人おことわり」と賃貸契約も結べなかった。そんなことで我が子の誇りを失わせたくない、と父はわたしが大学進学で上京する際に現金でマンションを買ってくれた。在日特権なんてものは存在しません。いま、カレン人の彼がそうしているように、苦労して一所懸命働いて稼いできただけです。
日本人だけでこの国は成立していない。今後はもっとそうです。それはみなさんにも分かっていることではないですか?
彼の年次の滞留期限は今年の2月2日でした。1月25日に彼から連絡が来ました。12月のはじめに延長申請をして、例年ならひと月で許可が下りるのに連絡が来ません、あなたから入管に問い合わせてくれませんか、と。仕事しながら入管に電話しましたが、通じたのは大代表だけで、その大代表も「指定書になんて書いてあるかしらべてからもう1回かけろ」と最初は言われたのに、次にかけたら「申請番号は?」と。申請番号だったら最初から知ってるわ。この対応、組織のシステムとしても無能だと思うし、意地悪したいだけにも思える。そして「そういう案件はこちらに」と言って教えられた電話番号には100回くらいかけたがまったく通じませんでした。日本語と英語で「大変混みあっているので後でおかけなおしください」というアナウンスが流れて通話は切れました。26日のことです。
通知が来ないまま2月3日になれば、彼は「不法滞在者」という犯罪者です。彼は日本に職を持ち、マンションも借りていて、もし2月1日に通知が届いて更新がなければ、日本を出て行かなければならない。翌日も電話しまくり、やっと入管に電話が繋がりました。ほんと、いつも思うけどめっちゃ横柄なんだよなあ。こんなに横柄な役所ないよなあ。「いま審査中で、いつ頃送れるかはわかりません」と言うので、「でも彼のビザはあと数日で切れるんです」と言うと、「申請している期間は滞在が2か月延びます」と。それ、どこに書いてあんねん。「では、4月2日ということでいいんですか?」「はい、そこまでには送るんで」と。「そこまでって、4月2日までにってことでしょうか?」「そうです」。ハァ? 前日に通知来たらどうすんだよ。もしノーなら、翌日荷物をまとめてミャンマーに帰れと?
電話か直接入管に行くかしか手立てがないのって、いまどきシステムとしてもめちゃくちゃひどいと思う。先進国として恥ずべきシステムでしょう。ネットで番号入力して本人確認したら分かるようにしたってくれよ。まだ在日韓国人が国外に渡航する際に再入国許可が必要だった時代、わたしが申請したときも、朝9時に着いても200人待ちとかで、当時は大手町庁舎のボロいビルの地下で(まず、なんで地下?って思ったわ、ドストエフスキー思い出したわ)、すし詰めで待たされて、なぜか昼休憩を取るので午後には500人待ちとかになってて、職員が母音たっぷりのカタカナ日本語で名前呼ぶんだけど、それを自分の名前だと分かる外国人はどれくらいいるのだろうか。言われてることが理解できていなさそうな外国人に対しても職員は何度も同じことを日本語オンリーで話していて「おまえ、いい大学出て法務省に入ったんちゃうんかい、英語くらい喋ったれよ!」と思ったものです。ちょっと調べてみたらつい最近でも公的には「日本語と英語でアナウンスしてます」と言ってるけど実際入管に行ってみたら日本語オンリーだったというジャーナリストの記事に行き当たりました。さすが大臣が「死刑のハンコついてるだけで旨味のない仕事」とか言うわけよね。人権なんてないんだよ、この国には。
彼が不安な日々を送っていることを、わたしはここに記録しておきたい。不安ってさ、やだあ、体重増えちゃったー、子どもの受験がーとか、そんな呑気なものではないんですよ。生きるか死ぬかについての不安なのです。
考えてみてほしいのです。自分のこととして。
名古屋入管でのスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんの死亡ニュースは話題になりました。ああいうことが程度の差はあっても日常茶飯で起きています。
日本国籍を持っていて入国管理局を訪れる人は、弁護士などの専門分野の方や支援活動をされている方しかいないと思いますが、本当にすべての日本人が行くべきところです。そこでは、外国人が外国人だというだけで犯罪者扱いです。わたしも何度もそういう目に遭いました。だけど、わたしは日本語が堪能です。だから問題はない。でも行くたびに本当に嫌な思いをしました。なぜわたしは外国籍というだけで、このような扱いを受けなければならないのか、この強制収容所みたいな施設はなんなのだ、といつも思うのです。
入管問題に詳しい弁護士の児玉晃一氏によれば、入管の収容所ではレイプもあったそうです。日本の国家公務員による外国人に対するレイプです。誰も起訴もされていません。女性収容者が「電話をかけたい」と言うと「おっぱい触らせてくれたらいいよ」という職員もいるそうです。信じられない? でも事実です。これが日本のありのままの姿なのです。「お・も・て・な・し」とかインバウンド需要が…とかいう話を聞くたびに鼻白んでしまうのは入管の体質を身をもって知っているからです。みなさんにも知ってほしい。知って、考えて、行動してほしいのです。
現政府は今国会で入管法の改悪を行おうとしています。あなたたちは平気な顔をしてこれを通すのですか? 自分は日本人で、外国人の身に起きることは関係ない? 強制送還されれば命の危険がある難民を「3回以上難民申請した」という理由で、国外退去させるのでしょうか? それは間接的な殺人ではないのですか? あなたの良心はどこにあるのですか? 想像力は?……いったい、どこに?
そして。
写真を載せてるから、わたしが着ているのは、そのカレン族の民族衣装だということはお分かりになるかとは思いますが、なんと彼のお母さまの手織りの衣裳です。
手織りの民族衣装じたいは多分お金を払えば日本で買うこともできるでしょう。でも、これは彼のお母さまがわたしのために織ってくれたものなのです。いただくなんて恐縮すぎて、お金をお支払いしたいと話したら「これは、わたしたち家族から、あなたへのプレゼントです」と言われて、ありがたく頂戴しました。たいせつにします。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
“わたし”の居場所
2022年9月14日
スタッフ 鍵本 幸子(かぎもと さちこ)
今夜も「せいわ自主夜間中学」教室に来ると“ホッとする”落ち着く空気感が漂い、生徒さんたちの学びの場は、短い時間でも“学びたい”気持ちがにじみ出て、ほほえましい光景が目に映ってくるのです。
「文字や漢字が解らず、役所の書類や病院の問診票が書けない等」、日常生活を円滑にするため、少しでも手助けさせてもらっているのが私達スタッフ一同です。
「せいわ自主夜間中学」は学ぶ機会を得られる場、楽しく和やかな教室です。国籍、年齢、異なる多様な生徒さんの明るい笑顔から“学びたい”気持ちの前向きな姿にむしろ、私自身生徒さんから様々なことを学ばせてもらっているのです。 受容的な場、ホッとする場、居場所を見つけて。
「自主」と「夜間」と「中学」と
事務局員 松川秀之
西和自主夜間中学は、24年あまり前に、ここ王寺町のかつての中央公民館をお借りして活動が始まりました。多くの方々からの支援に支えられて活動を始め、王寺町をはじめとする西和地区の町々からの支援、配慮をいただき、県教育委員会の支援、応援もいただきながら、活動を続けています。
もともとは、子どものころに諸事情で学校に通えなかった人たちが、大人になってから学校の勉強を学び直し、学校で勉強することを取り戻す目的を持った、公立中学校夜間学級創設運動にならった取り組みでした。差別などの社会的な事情や、家庭の経済的な事情、あるいはいじめなどの事情で、通いたくても学校に通えず、悔しい思いを晴らせない人たちが、ちゃんと公の学校で勉強し直せる場所を作ることを目指した市民運動がそのモデルでした。
開設当時は、公民館の和室をいくつか借りて、数人~十数人の生徒さんとスタッフが、休憩を入れながら(休憩時に食べるパンも差し入れしていただいていました)、勉強し、世間話や身の上話をしていました。差別やいじめに遭って学校に通えなかった日本の方や在日コリアンの方、アジア諸国から結婚などで日本に来て言葉や生活上の差別に困っている方、仕事を求めて家族で日本に移り住んでいろいろな困りごとを抱えた方、さまざまな方たちが、学校での学習を少しでもし直し、生活のために日本語を学び、これまでの思いを心おきなく話し、あるいは心おきなく母国語を話していました。生徒さんもスタッフも、仕事を終えて疲れた夜に、少しだけ心を開ける場所でした。
スタッフも、サラリーマン、主婦、学校の教員、仕事をリタイアした人などさまざまで、日本語だけでなく、英語や数学などの勉強も、生徒さんの求めに応じて、手助けできるスタッフがマンツーマンで援助していました。これらは今も続いているスタイルです。
一方で、不登校だが勉強をしたい中学生、数年後には母国に帰るが少しでも日本語を学びたい留学生や外国語講師も顔を出すようになりました。これらは、公立の学校としては受け入れる条件に外れる人たちでしたが、「今、切実に学習を必要としている人なら、自分たちができる手助けをしよう」「市民の自主的な活動であるから既存の学校のルールと違っていい」と、受け入れました。
生徒さんは、はじめは日本で生まれ育った方、在日コリアンの方、フィリピン出身の方、南米からの日系人の方が多かったのですが、それに加えて結婚や就労でアジア諸国から来られた方が増えています。そういうわけで、現在は日本語を学ぶ方が多いのですが、もちろん他の教科学習もおこなっています。外国から来られて日本に住んでいらっしゃる方のお子さんが、これから日本で生きていくために必要な勉強を、手助けしたりもしています。
これが、西和自主夜間中学の今の姿です。「夜間」であること、「中学」の名を持つこと、「自主」という言葉の意味するところは、このようなものです。
これからも「西和自主夜中(せいわじしゅやちゅう)」は、いろんな市民のボランティアスタッフが、日本で暮らすうえで今切実に学習を必要としている人の力になれたら、と扉を開いて待っています。
日頃から支援、応援をいただいている一人一人の市民の方々、王寺町をはじめとする西和地区の町々、県教委に感謝いたします。ただ、この自主夜中を必要とする人たちは、まだまだいらっしゃると思います。これからの運営のために、より一層のご支援をお願いします。